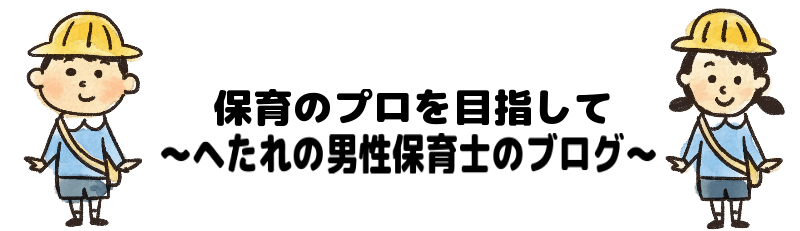保育士の仕事をしていれば、子供達がけんかをしているその場に遭遇してしまう、なんてことは日常茶飯事です。
子供のけんかを一々仲裁していればきりがありませんし、それに子供はそもそも自分でけんかを終わらせる能力を持っていますので、ある程度は容認するのも良いです。
子供とけんか
3歳頃までは、子供が泣けばすぐに親が手助けをするため、全ての欲求は満たされたまま生活を送ることになりますが、幼稚園に入園してしまえば全てが自分の思い通りにいかないことも多々あります。
おもちゃをめぐってけんかをすることもあれば、遊具をめぐってけんかをすることもありますが、これらは全て欲求が満たされないことによって引き起こされるけんかです。
子供は他の子供と一緒に生活を送ることで、「欲求が満たされない場合もある」ことを学ぶことになります。
そして、溜まってしまったフラストレーションをどのように解消していくか、けんかの相手となる子供と一緒に考えていくことで、社会性を身に付けていくことになるのです。
例えばおもちゃで遊びたいならば、けんか相手と一緒に遊ぶことや遊ぶ順番を決めることなどの解決策くらいは、友達と一緒に考えて自分達で決められます。
これによって、問題が発生した際にどのように解決していくか、社会性やコミュニケーション能力がぐんぐんと成長することになるのです。
保育士の仕事をしていると子供のけんかに何度も鉢合わせることになり、これ以上面倒になってしまっても厄介ですし、また子供にけがをさせてしまった場合には責任問題にもなりかねませんので、ついつい仲裁をしてしまいがちですが、子供達のけんかは学びの場でもありますので、保育士としてはある程度は見守ってあげるだけという立場にいることも必要です。
止めなくても良いの?
けんかは子供が成長するために必要な良い機会ではありますが、しかし全てのけんかを見守るだけではいけません。
中には止めて仲裁してあげるべきけんかもあります。
子供が怪我をしてしまいそうな程激しいけんかだった場合や、子供達から手助けを求めている場合、複数対一人のような一方的になりそうな場合には、保育士が仲裁に入るべきです。
けんかをしているのは子供ですので、まだまだ未熟で思いや考えを言葉に言い表せられないケースもありますし、感情的になっていることもあります。
そんな時には、保育士は子供の気持ちを代弁するスポークスマンとして仲裁しなければなりません。
また両者が感情的になってわけが分からない状態になってしまった場合には、一度子供達を落ち着かせて、子供でも分かりやすい噛み砕かれた言葉で分かりやすく説明してあげる必要があります。
保育士としては子供達に怪我を負わせるわけにはいきませんので、適度に様子を見てあげて、かといって学びの機会を取り上げてしまわないような上手な対応が必要ですね。