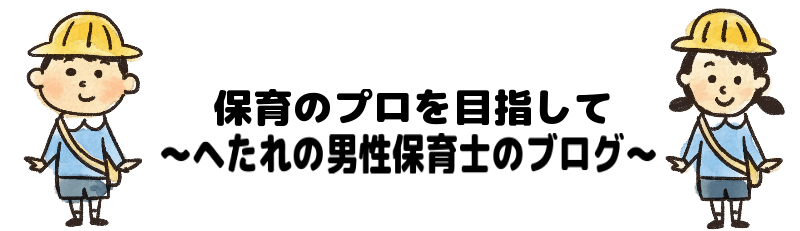男性と女性の大きな違いは、体格や性格だけでなく、声もこれに含まれます。
男性特有の低い声には、男性らしいたくましさが込められていたり、使い方次第では落ち着いた印象を出したりすることが可能です。
しかしながら、男性の低い声は必ずしもプラスに働くというわけではありません。
特に保育士という仕事からしてみれば、低い声が子供達の恐怖心を喚起させる原因にもなりかねませんので、マイナスに働くケースも多々あるのです。
怖い先生!
常に低い声で子供達と接していると、「怖い先生」という印象を与えてしまうことにもつながりますので、注意しなければなりません。
ただでさえ低い声なのにも関わらず、叱る際にも同じトーンで叱ってしまうと、常に怒っている人という認識になってしまいます。
そのため、できることならば普段は少しだけ高めの声で子供達と接し、そして叱る際には低いトーンで、といった具合に声色を使い分けて接する必要があるのです。
男性の弱点である声の低さは使い分けによって長所にもなり得ます。
子供が喜怒哀楽を感じ取ることができないこともありますので、大人からしてみれば少しオーバーな表現であったとしても、そのくらいの誇張表現がちょうど良いかもしれません。
少し大袈裟に喜んであげながら子供達とコミュニケーションを取ってみるのがお勧めです。
怖い先生というイメージが固まってしまうと、保護者の方々からも心配されることになったり、また単純に子供達から畏怖される存在となり、保育という仕事もやりにくくなります。
その他にも、他の教員の方々からも心配の声が上がることもありますので、仕事をしやすい環境を整えるためにも、怖い先生というイメージを植え付けることは避けるように努力する必要があります。
興味津々
子供達は新しいことに対しては何にでも常に興味津々です。
目新しいことがあればすぐに質問をしてきて、ある程度理解するまで質問をやめません。
そして覚えたことはすぐに使います。
これは勿論良いことばかりではありません。
たとえ悪いことであったとしても覚えればすぐに使いますので、保育士はその点にも充分に注意して仕事をこなしていく必要があります。
特に口調や言葉遣いについては、この傾向が顕著であり、また保育士側からしてみても注意が行き届かないことがありますので、配慮しなければなりません。
保育士も聖人ではなく一人の人間ですので声を荒らげることもあるとは思いますが、感情に任せて「おい」とか「バカ」というような乱暴な言葉遣いをしてしまうと、その言葉が子供達に伝播することになりますので、感情は押し殺してでも丁寧な言葉遣いを心掛けなければならないのです。
何にでも純粋に興味を示す子供達を正しい道へ導いてあげることも、保育士の仕事です。