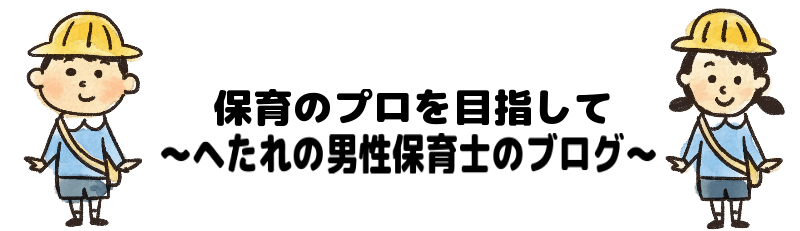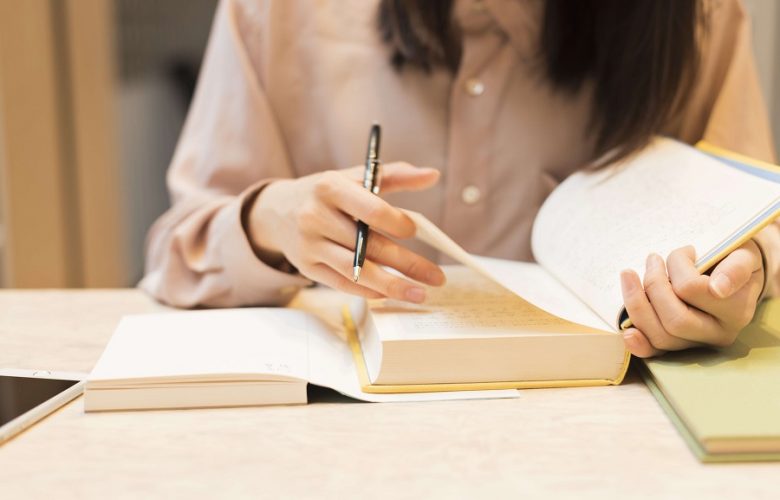保育士になるためには、厚生労働省が指定する保育士を養成する学校を卒業して資格をもらうか、もしくは国が実施する保育士の試験を突破して資格を取得するという2つの方法があります。
学生時代から保育士になろうと考えていれば、専門学校や大学などに進学し、卒業をしてそのまま資格を取得するという流れで夢を追えば良いのですが、しかし社会人になってから保育士になりたいと思う人も中にはいます。
そういった方の場合は勉強をして試験に合格する必要があるのです。
受験者数と合格率
保育士の試験は毎年1度だけ実施され、全国にいるこの資格取得希望者と一緒に試験を受けなければなりません。
受験者数は、以前は3万人から4万人程度でしたが、最近では増加してきており、およそ4万人から5万人となっています。
平成24年の受験者数が過去最高で5万2千人となっており、平成25年では5万1千人と少し減少していることから、これから先は横ばいの状態になることが予想できます。
しかし、受験者数は資格の取得とあまり関係はありませんので、この数を知っても同様しないようにしましょう。
参考までに合格率を出しておくと、およそ10%から20%という合格率となっており、このことから簡単に取得できる資格ではないということが分かります。
ここ数年で最も合格率が高かったのは平成19年の20.4%で、最も低かったのは10.6%となっています。
このデータからも分かるように、試験の難易度は年によって異なり、運が良ければ簡単な問題ばかりの試験となる可能性もあります。
定員制の試験のように資格を取得できる人数はあらかじめ決まっているわけではありませんので、これらのデータはあまり意味がありません。
あくまで保育士を目指す際の参考程度に考慮しておいてください。
合格ラインについて
試験の合格率は勉強とはあまり関係ありませんが、合格に必要な得点ラインは考慮すると良いでしょう。
保育士の試験に必要な合格点はおよそ6割と言われています。
問題は全て5択のマーク方式になっていますので、もしも問題を解く時間が無くなってしまった場合には、最低でもマークだけはしておくようにしてください。
もしかしたらカンで正解するかもしれません。
合格に必要な得点が6割であることは分かっているので、勉強法もこれに合わせて行うと良いでしょう。
6割必要であるということは、逆に言えば4割は間違っていても合格できるということです。
これは単純な計算ですが、参考書の中の6割だけ理解できていれば資格を取得できるわけですので、もしも勉強する時間があまり残されていないという場合には、全てを覚えようとはせず、出題されている傾向に応じて勉強を進めていくと良いでしょう。