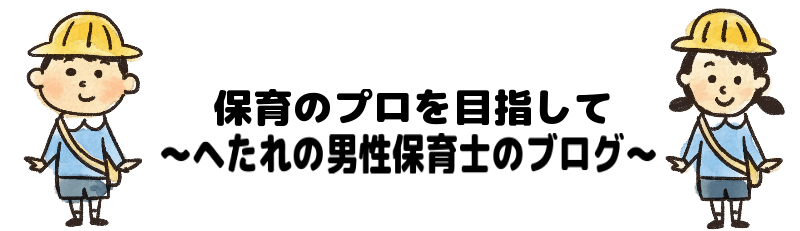男性の保育士はまだまだ少なく、働く環境としては女性主体の考え方や制度などが良くも悪くも根強く残っているものです。
医療施設などに併設されているような保育所などで働く場合には、他の仕事をしている男性の方々もいらっしゃいますので、そういった考え方だけが跋扈しているわけではありませんが、これまで男性の保育士を雇ったことが無い幼稚園や保育園の場合にはこの傾向が強く、男性にとっては仕事をし辛い環境になっていることが多いです。
いやがおうでも
男性からしてみれば嫌なことでも、女性主体の環境からしてみれば、男性保育士はいやがおうでもやらなければならないことが多々あります。
例えばエプロンの着用です。
常にエプロンをかけて子供達の面倒を見るということは女っぽいことですので、一部の男性からしてみれば嫌なことですが、しかし園の規則によって着用が義務付けられていることも少なくありません。
エプロンは保育士が自由な物を選べるという園もありますが、中には園が用意したエプロンをかけるように義務付けられることもあります。
そしてエプロンが女物しかなくて、それを手渡されたならば、男性保育士はいやがおうでもこれを着用しなければならないのです。
色が淡いピンク色でデザインも可愛らしい、キャラクターの刺繍が施されているようなエプロンであったとしても、義務化されていれば仕方ありません。
子供に馬鹿にされようとも、そのことで叱るのはどうも間違っている気がしますし、あまり強くは言えず、心のもやもやが溜まっていくという事態にも…。
それでも我慢しなければならないわけですので、男性の保育士はそういった環境でも柔軟な対応できるような心の広さを持っていなければならないのです。
なぜエプロンの着用が義務化されている?
多くの園で保育士のエプロン着用が義務化されていますが、これにはちゃんとわけがあります。
まず1つ目は園児達が保育士を保育士と認識させるという理由です。
子供達は相手がたとえ大人だろうと、単なる人としてまず認識することになりますので、他の大人と区別してこちらを認識してもらうためにもエプロンを常に着用する必要があるのです。
2つ目は、警戒心を緩和させるという理由です。
女性ならばまだしも、大人の男性は大柄な体躯をしているもので、これが恐怖と警戒を生む原因になってしまいます。
可愛いデザインのエプロンはこれらを緩和させる効果があり、子供達とのコミュニケーションを取るきっかけにもなります。
エプロン着用を義務化しているのにはこういった理由がありますので、男性からしてみれば少し抵抗があるとは思いますが、そこは慣れるまで我慢する必要がありそうです。